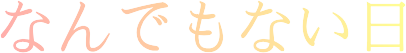午前の授業の終了を告げるチャイムは、同時に昼休みの開始を告げる。学生たちの束の間の解放。先ほどまでは静まり返っていた校舎内が、数分後には生徒たちの会話と足音で賑やかに彩られる。
授業中の独特の緊張感から解きほぐされ、解放感からくる清々しさを顔に浮かべた生徒たちで混雑する廊下を、紫原はのろのろと進んでいく。人は多いが、ぶつかる心配はなかった。規格外に大きい紫原に、誰もが一歩避けるからだ。モーゼの出エジプトみたいだ、と紫原はなんとなく思う。映画で観た、海が割れるシーンが蘇る。
購買では絶えず生徒と店員のおばちゃんの声が行き交い、活気づいていた。おばちゃんこれ、あいよ200円ね。こんなやりとりがエンドレスに繰り広げられている。お互い、値段はすでに脳内に刻まれているかのようなスピーディーなやりとりだ。実際、どれにしようかと悩んでいる時間はない。悩んでいる間に選択肢は次々に失われてしまうので、悩むことが意味をなさないからである。
紫原は人よりも高い目線で、パン屋の名前の入った淡い黄色の番重に並ぶ、菓子パンを眺めた。ラインナップはいつもと変わらない。条件反射のように3つのパン―ーサンドイッチと、コロッケパンと、チョコクロワッサンの3つだ――を掴むと、店員の手のひらに百円玉を4つ落とした。阿吽の呼吸といっては大げさかもしれないが、生徒と購買の店員の間には似たようなものがある。
購買から離れ、多少賑わいが緩和された廊下をひたひたと歩く。足を踏み出すごとに、まとめてつかんでいるパンのビニールが擦れて、シャカシャカと音を立てた。息を乱すわけでもなく、なんなくと階段を上りきった紫原は、廊下の突き当たりの教室の前で足を止める。
ドアに手をかけ、少しだけ開けて耳を澄ましてみる。数センチの隙間から微かに聞こえる、心地よい音。
いる、そう確信した紫原は、ガラリと遠慮なくドアを開け放つ。
「やほー、ちん」
その声に、音楽室の隅に座り込んでギターの弦を撫でていたが、うっとおしそうに顔を上げた。
***
「あのさ紫くん、一応こっそりやってんだからさ、少しは遠慮しながら入ってきてよ」
「はあ?なんで?」と気の抜けた返事をしながら、紫原は音楽室の窓辺に腰を下ろした。こんな日は、差し込む日差しでじんわりと暖かい。サンドイッチの封を豪快に破り、中身にかぶりつく。見る見る形を失っていく白いかたまり。もそんな紫原の調子に、諦めたように溜息を1つこぼすと、再び黒いボディーのアコースティックギターを鳴らし始めた。
は時々こうして昼休みの音楽室に忍び込んでギターを弾くことがある。ギターは音楽室の棚に並べられている、年代物のアコースティックギター。チューニングのたびに切れてしまうのではないかと冷や冷やする、もう長い間張り替えられていないであろう弦。優しく弦を撫でるだけで、周りの音が遮断されたこの教室の空気が震える。空気を揺らす振動さえ、この無音を破るのは億劫だと思っているようで、響くギターの音はとても遠慮がちだ。広い音楽室に漂う、不釣り合いなほど微かな音。
練習したいという感情とは別に、ふとこの体温のような音が恋しくなる時がある。そうしていてもたってもいられなくなると、はここに足を運んでいた。
それをどこからか紫原に知られてしまい、現在に至っている。ずかずかと無遠慮にの時間に踏み込んでくる紫原を、はうっとおしいと思ったが、何を言ったところで改める気がないと分かると、それ以上ああだこうだ言うことをやめた。聞き分けがないというか頑固というか。
見た目はこんなにも緩そうなのに、とサンドイッチを頬張る紫原を一瞬見る。
「なにちん。今、悪口言ったでしょ」
「言ってない。心の中で言ったけど」
「言ってんじゃん。ひどい。オレまじ可哀想」
紫原の勘の鋭さには、も舌を巻く。今日だって、ここに来ることがなぜ分かったのだろう。たまたまこの場所にいることを、結構な確率で突き止められている。(不本意ながら)
見えないものを嗅ぎ分ける嗅覚は天才的と言っていい。才能に何故と理由を問うことの無意味さをは知っていた。この学校には、凡人が口を出せないような類稀なる才能の持ち主が少なくない。
「紫原くんってすごいよね。うん、すごい」
「何の納得。意味わかんねーし」
「いっぱいすごいとこあるよね。背が高いし、バスケうまいでしょ。お菓子を胸やけしそうなほど食べられるし、頭緩そうなのに実は賢いし。それから」
「はあ?そんなこと何一つすごいなんて思ってないくせに何言ってんの」
紫原は眉毛をつり上げてぴしゃりと言い放つ。
鋭いなぁ、とは苦笑を浮かべると、同時にコードを押さえていた人差し指の先に電流のような痺れが走った。ぴりっと痛みが駆け抜ける。
「いっつ……」
痛む指先を見ると、うっすらと赤色が広がっている。指先の皮膚が数ミリひび割れて、血がにじんでいた。
「ちん血出てる。痛そー」
痛そう、というわりに、言い方があまりにも他人事といったふうで、思わずは笑う。紫原らしい。他人のこととなると驚くほど冷めている。例えばが今ここで倒れたとしても、助けを呼んでもらえるかどうかも疑わしい。
は制服の胸ポケットから絆創膏を取り出す。慣れた手つきで包装を破っていると、いつの間に隣に立っていたのか、紫原が横から絆創膏をひったくった。
「なんとまあ横暴な」
「うるさい。指出して」
「……とりあえず、私が倒れても助けは呼んでもらえそう」
「なんの話」
絆創膏が剥がれないように、指で軽くつまんでくっつける。紫原のバスケットボールを片手で掴んでしまうほど大きな手と長い指が器用に動く。の手もクラスメイトの女子と比べれば小さい方ではないのに、紫原の手と並ぶと、子どもの手だと錯覚してしまいそうになる。
「ちんの手、冷たい。オレの体温、もってかれたし」
紫原は、の手を解放すると、その大きな手を擦り合わせて大げさに息を吹きかけた。どうしてくれんの、とでも言いたげな目に見下ろされて、はふといじわるを思いつく。
口角をあげて、目を細めたの表情に、紫原の眉間に皺が寄る。何企んでんの、という言葉より一歩早く、
「絆創膏巻いてくれてありがとう。お礼に、私の冷たい手でしっかり温めてあげる」
の小さな手が、ぎゅっと紫原の大きな手を包んだ。
「!!?」
氷水に突き落とされたかのような衝撃に、もはや声も上がらない。
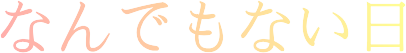
次の日、の机の上にはハンドクリームが、紫原の机の上にはホッカイロが置かれているのを、クラスメイトたちが不思議そうに眺めていたとかなんとか。
(あれ、このハンドクリーム、昨日紫っちが帰りにドラッグストアで買ってたやつ?)
疑問をもった男が一人。
2014.02.28